仕事と受験勉強を両立でき、しかもステップアップにつながるということで人気のある資格はたくさんあります。
中でも、簿記2級(以下、特に注記がなければ日本商工会議所及び各地商工会議所主催簿記検定試験2級を指す)と宅地建物取引士試験(以下、宅建士試験)は毎年たくさんの人が受験することでも有名です。
実はこれらの2つの資格は、両方持っておくと何かと役に立ちます。そこで今回の記事では、違いを徹底分析した上で、両方取得するメリットについて解説しましょう。

簿記2級と宅建士試験の違いを徹底分析
以下のつの視点から、簿記2級と宅建士試験の違いを徹底分析してみます。
- 勉強時間
- 年間の試験実施回数
- 試験内容
- 合格率
- 活かせる業界
違い1.勉強時間
一般的に、簿記2級の場合、必要な勉強時間は300~350時間程度と言われています。既に簿記3級に合格していた場合でも、200~250時間は欲しいところです。
一方、宅建士の場合は、不動産会社での実務経験があるかによって異なります。少ない人では100時間程度で済みますが、多い人では500時間を超えるケースもあるため、平均して200~300時間程度といったところでしょう。
これらの数字だけを見ると、簿記2級と宅建士で必要な勉強時間には大きな差はないかもしれません。
ただし、これまでどんな勉強、仕事をしてきたかで必要な時間は異なるため、あくまで1つの目安程度に考えてください。
違い2.年間の試験実施回数
まず、宅建士試験は1年に1回しか試験を行いません。7月が出願期間で、10月が本試験というスケジュールが通例でした。しかし、2020年と2021年は新型コロナウイルス感染症の影響により、本試験は10月と12月に分けて行われています。
一方、簿記2級の場合、会場試験は年3回(6月、11月、2月)実施です。ただし、ネット試験を利用すれば、施行休止期間はあるものの、基本的にほぼ1年中受験できます。
違い3.試験内容
簿記2級の場合、商業簿記と工業簿記の2科目から出題されます。基本的には会計分野の知識のみを問う試験です。
一方、宅建士試験の場合、宅建業法、権利関係(民法など)、法令上の制限、税・その他の4科目から出題されます。宅建業=不動産会社で働く上で必要な知識を問う試験でもあるので、範囲はかなり幅広いです。
違い4.合格率
まず、宅建士試験の場合、合格率は平均して20%を切ります。令和3年度の場合の合格率は、10月試験が17.8%、12月試験が15.8%でした。
一方、簿記2級の場合は回数、実施方式によってまちまちです。まず、過去3回分(第159回~161回)の会場試験における合格率は以下の通りです。
- 第159回(2021.11.21実施):30.6%
- 第160回(2022.2.27実施):17.5%
- 第161回(2022.6.12実施):26.9%
2021年4月~2022年3月に実施されたネット試験の場合、合格率は38.1%にも達しました。
合格率だけで言えば、宅建士試験のほうがはるかに難しいでしょう。
違い5.活かせる業界
宅建士資格が活かせるのは、なんといっても不動産業界です。宅建業法では、宅地建物取引士の設置義務が設けられています。
簡単に言うと、営業所などの事務所には、業務に従事する者5人に対し、必ず1人以上の宅建士を置かないといけません。つまり、スタッフが11人いる事務所の場合、最低でも3人のスタッフは宅建士でないといけない計算になります。
このような背景があるため、不動産業界では宅建士試験に合格していることが、採用や昇進の条件になっているのも珍しくありません。不動産業界以外ではあまり使い道がない資格ですが、食いっぱぐれがないのが大きな強みです。
一方、簿記2級はお金が動く場所」ならどこでも活かせる汎用的なスキルが身につきます。
一般企業の経理関連部署や税理士・会計士事務所で重宝される傾向がありますが、他のところで使い道がないわけではありません。
簿記2級と宅建、両方持つメリットは?
ここまでの内容を踏まえ、簿記2級と宅建士の両方に合格するメリットについて考えてみましょう。
メリット1.数字に強くなる
宅建士合格者が不動産会社の営業担当者になるのは珍しくありません。自分たちが扱う物件を買ってもらう、借りてもらうための提案ができないと営業成果は出せませんが、そこで簿記2級が役に立ちます。
簿記2級の知識があれば財務諸表を読めるようになるため、顧客企業の経営状態を把握しやすくなります。そこから適した提案ができれば、数字にも跳ね返ってくるでしょう。
メリット2.キャリアチェンジしやすくなる
宅建士合格者が簿記2級を持っていると、不動産会社の営業職から経理職へ、というキャリアチェンジもしやすくなります。簿記2級があれば一般的な企業の経理事務は十分にこなせるようになる上に、宅建士の勉強や実務を通じて、不動産会社ならではの特殊な事情も理解できるためです。
いずれにしても持っていて損になることはないので、多少時間をかけてでも両方取得するのを目指してみましょう。


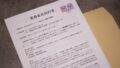
コメント